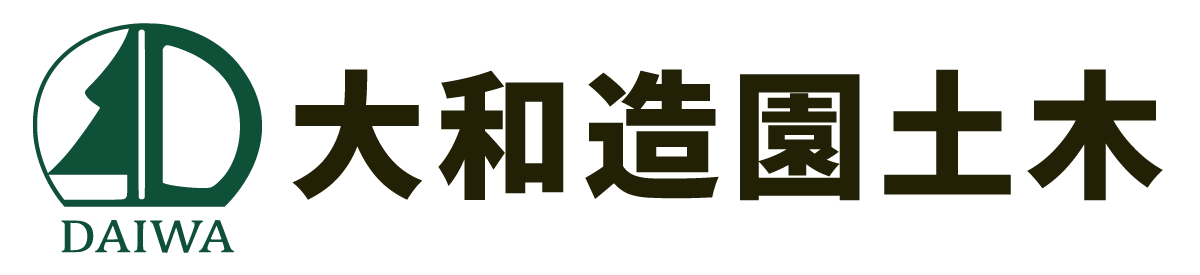お客様からよくいただくお問い合わせについて、特にお寄せいただくことの多い問合せを、植栽・移植編、土壌編、病害虫編、庭づくり編に分類して提供しております。
植栽・移植編
庭に木を植えたいのですが、場所、環境などの注意点を教えてください。
樹木の育成にとって大切なのは、日当たり、水はけ、風通しの3点です。日当たりは植える場所のそばに家やその他の樹木など、日当たりの邪魔するものがないかを調べます。日陰のでき方で、植えることのできる木が決まりますので、北側の日当たりは注意して調べた方がよいです。風通しも同様に家や周りの樹木に影響されます。
水はけは、土質によって決まります。土質は改善することが可能なので、水はけが悪いと感じる場合は、調べて改善する必要があります。
庭木の配置をするのには、どのような工夫をすればよいですか。
例えば、狭いスペースに常緑樹をたくさん植えると、日のよく当たらない冬には部屋の中が暗くなってしまいますが、冬に葉を落とす落葉樹なら日照を確保することができます。また、庭を広く見せるには手前に低木を植え、奥に高木を植えると良いでしょう。 高さの違う木を組み合わせて植えると、変化があって、かつバランスのとれた庭ができます。
庭木に毎日水をやっているのに枯れてしまいました。どうしてでしょう。
植えつけの時に十分水を与えれば、毎日のように水をやる必要はないです。土が乾いてきたら水をやるようにするのが良いでしょう。ただし、夏には、たくさん水を与えてください。朝夕の打ち水程度の水やりは、地熱を下げるだけで、根が吸収するまでには足りません。
アオキが何年たっても実がつかないのですが、どうしてでしょうか。
アオキは、雌雄異株で、雌株には実がつきますが、雄株には実をつけません。また、雌株だけでも結実しにくいので、近くに雄株を植えると良いでしょう。
土壌編
庭木にはどのような土が適していますか。
庭木にとっては、通気性がよく保水性と水はけに優れ、養分を含んでいる土が理想的です。
スコップなどで簡単に掘れる土で、黒色または、褐色で軽くふっくらしていれば、水はけがよくて乾燥しにくい庭木の育成に適している土だと考えられます。
庭を芝生にしたいのですが土が悪いようですどうすればよいのですか。
芝生がよく生育するには排水、肥料、日当たり等の条件があります。現在の土に宿根の雑草があれば除草剤でなくするか、入れ替えの必要があるでしょう。排水の状況はどうでしょう。雨水がたまり、いつまでもあるような場合は暗渠排水をし、山砂当の排水よく、雑草種子の混入していない土に肥料分を加え、土を加えなくてはだめです。芝生地に良好な環境つくりをしなければ後のメンテナンスが大変です。
挿し木用の土はどんな土が良いのでしょうか。
用土は普通、赤土、鹿沼土、川砂などが用いられる腐植質を含まないものであれば身近なものでも良いでしょう。庭に挿し床を作る場合には赤土か鹿沼土で深さ15~20cmの床を作る。落葉性の低木類で活着しやすい物は、黒土のような畑なら直接挿してよい。挿し箱や鉢挿しは細かい用土がよいでしょう。
土壌改良材について教えて下さい。
土壌改良材は、土の保水性や通気性を高めたり、逆に水はけを良くしたり、又は土のpHの調整などにより、樹木などの生育に適する方向に改善することです。土壌改良材にはさまざまな種類があります。大別すると次の種類になります。
1)有機質系
動植物の遺体を主とした加工物で、泥炭、亜炭系(ピートモスなどでpHに対する緩衝能を強める、保肥力の増大、腐植質の増大などの効果)、バーク系(土壌の膨軟化、微生物の活動を活発化する、土壌物理性の改良、保肥力の増大、養分の供給、腐植質の増加などの効果)などがあります。
2)無機系
鉱業製品を高温処理、粉末にして多孔性の物質に変えたものがほとんどです。これらは、表面積が大きく、塩基性置換容量、膨潤保水性が高いため 土壌の透水性や保水性を改良し、肥料分を吸着させます。
病害虫編
苗木にアブラムシがたくさんついています。どうしたらいいのでしょうか。
アブラムシは室内の鉢植えを含むほとんどの植物に発生します。 葉・茎・幹に口針を刺し栄養分を吸い取るため、異常発生すると木全体が弱り枯れてきたりします。
種類も多く根に寄生するもの、葉や新芽を縮れさせるもの、葉にコブをつくるものなどもいます。
また、枝葉にカビがつくスス病、葉がまだら模様になったり、縮れたりするモザイク病などをひきおこす原因にもなります。 対策としては、早期にオルトラン・スミチオン等低毒性殺虫剤を散布し駆除します。 予防としては、反射光を嫌うので、根元にアルミ箔などを敷いておくのも効果があります。
桜などに多い病害虫を教えてください。
てんぐす病と呼ばれる病気が多いです。
てんぐす病とは、ほうきのように無数の枝がでる病気です。
予防方法は冬の間に1~2回、ダイセンや銅水和剤、石灰硫黄合剤などを散布しておきます。
治療方法は、枝のつけ根から取り除き、癒合剤を塗っておきます。
カイガラムシの駆除方法を教えてください。
大きく目に付くものは、捕殺すればいいです。
薬剤で駆除するには、ふ化直後をねらうのが重要です。ふ化期が解ったら、スミチオン、オルトランなどを1週間おきに2~3回散布すれば効果が高まります。
ふ化期以外では、冬の休眠期にマシン油乳剤の散布が有効です。
マツケムシ(マツノカレハ)の退治を教えてください。
マツ類の針葉を食害する毛虫で4~6月頃盛んに葉を食い、時には丸坊主にすることがあります。
成虫は7~9月に現れ葉に卵塊を産みつけます。かえった幼虫は秋まで食害しますが被害は少なくあまり目立ちません。しかし越冬した幼虫は4月ごろから葉を暴食し,大害を与えた後,樹上で繭を作って蛹になります。防除の適期は抵抗力の小さい9~10月,あるいは4月~6月の若い幼虫期である適期にディプテレックス粉剤を散布します。
もち病がついて困っていますがどうすればよいでしょうか。
ツツジ、サツキ、サザンカ、ツバキ類によく見られ、葉、花、花芽などの一部や全体が餅のように膨らんで、その表面が白色の粉で覆われます。病原菌は枝や芽の部分に菌糸の状態でもぐりこんでいるものと考えられます。春、発芽とともに発病して病患部に白い粉をふき、つまり胞子を形成して飛散させます。 防除は白い粉をふきだす前の被害部を切り取って焼却することが最も大切です。白い粉(胞子)ができて飛散する頃に銅水和剤400倍、4-4式ボルドー液、ダイセン、ダイファー水和剤500倍などを散布しても有効です。
庭づくり編
庭を作りたいが何からはじめたら良いか?
まず、建物は洋風でしょうか?和風でしょうか?庭はどのようなタイプにしたいのでしょうか? 次に庭の目的は何か?を考えます。室内から観賞する為の庭にしたいか、外からの目線を遮断する為なのかを考えます。
3番目に何を庭に置くのかを考えます。植物はどんなものを植えるのか、草花を多くするのか、樹木を多くするのか。また、石やガーデンファニチャーのような小物を置くのかも全体のバランスも含めて考えます。
樹木はどのように選べば良いのか?
庭作りは好みに左右されます。樹木選びにについても同じです。ただ、プロの側からアドバイスをするときは全体のバランスが良くなるように注意します。
たとえば夏は木陰を作り冬は日当たりを良くするよう落葉樹を、居住スペースにあった場所に配置したり、近隣との視線を気にするのであれば常緑の樹木を配置したりします。 また、花木も開花が同じ時期だけに集中しないように時期の異なる樹木を選んだりもします。 ただ、これはあくまでもお客様の要望、好みが一番に優先しますので、針葉樹だけの配置もされる方もいます。自分の好みを確認しながら探してみてください。
庭造りにはどれだけの予算が必要か?
プランにもよりますし、規模や植物ひとつひとつの金額、小物を置きたいのであればそれぞれの金額も異なります。業者に全て造園工事を任せる場合でも同じです。
お客様の要望を伺い、プランを作り、見積りを出して初めて金額が明確になります。
最初に、「こうしたい」という要望を全部だして、見積りを出してもらい自分の予算に合うように調節して最終の金額を決めていってはどうでしょうか。
限られたスペースでも庭が作れるか?
敷地の条件によって自分の希望どおりに行かない場合があります。
このような場合は、植物の組み合わせや、植えこみスペースの形状に変化をつけるなどして工夫次第では広がりのある庭造りが出来ます。
狭いスペースでは、狭さを感じさせないように目線をさえぎらないプラン、庭のスペースが日陰にあたる時には明るい色の植物を配置したプラン、道路から玄関へのアプローチがまっすぐな時は目線をさえぎるようなプラン、植栽を少なくし石やレンガ、工作物などで変化を付けたプランなど条件に応じたアイディアは業者に相談することで解決方法が見つかります。
自分のスペースの弱点を逆に活かすことで良い庭造りにつながります。